2025年
-
動作分析
なぜ脳卒中患者は立ち上がりに失敗するのか?立ち上がり「5相モデル」の決定的瞬間とリハビリ戦略

なぜ今、立ち上がり動作(STS)の「質」を問うのか? 立ち上がり動作(Sit-to-Stand: 以下、STS)は、ほぼ...
続きを読む -
動作分析
立ち上がり動作の「なぜ」を解き明かす– 歴史的論文を再考する –

本記事は、1990年に発表されて以来、立ち上がり動作(STS)分析の「標準」として世界中の臨床家・研究者に引用され続ける...
続きを読む -
リハビリ評価
健常者と脳卒中患者の方向転換動作の質の違いとは?
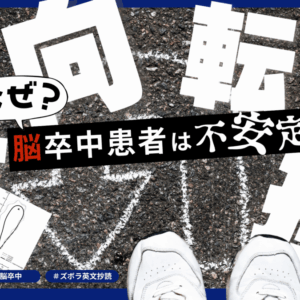
序論:なぜ方向転換の「時間」だけでなく「質」を評価べきなのか? 療法士として臨床に立つ我々は、日々、患者さんの「歩く」能...
続きを読む -
リハビリ評価
TUGの臨床応用 ―滑らかさ・二重課題・運動イメージによる多角的アプローチ―
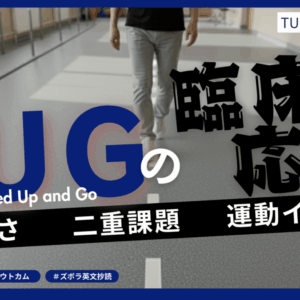
序文 前回のTUG【前編】の記事では、TUG評価が従来の単純な時間計測から、動作の「質」を問う多角的な評価へと革新されて...
続きを読む -
リハビリ評価
TUG評価の革新―時間計測から動作の質的分析へ―
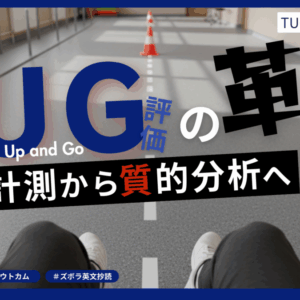
序章 -時間計測から動作の質的分析へのパラダイムシフト- Timed Up and Go (以下、TUG) Testは、...
続きを読む -
ハンドリング
筋の生理学と適応的可塑性:長さ-張力関係の動的解釈とハンドリングの理論的根拠
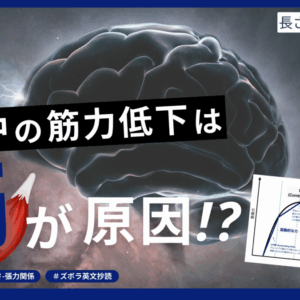
序論:脳卒中後筋力低下の多因子性と臨床的課題 脳卒中リハビリテーションの臨床現場において、我々が対峙する筋力低下は、単一...
続きを読む -
ハンドリング
最新研究から考察する立位分析のエビデンスと実践応用

序論:立位分析の「常識」をエビデンスで問い直す セラピストにとって、患者さんの姿勢を評価・分析し、治療介入を行うことは日...
続きを読む -
ハンドリング
ハンドリングの科学的根拠について

なぜ今、「ハンドリング(タッチ)」の科学的根拠が重要なのか セラピストにとってハンドリング(タッチ)は、日々の臨床の根幹...
続きを読む -
ハンドリング
動かなくても「意図」するだけで予測的姿勢調節(APA)は作動する
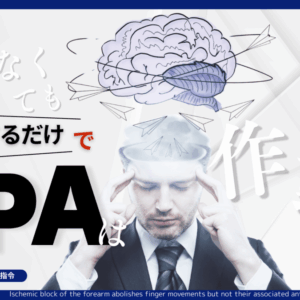
運動を行う前に姿勢を安定させる「予測的姿勢調節(APA)」は、私たちのあらゆる動作を支える重要な脳機能です。 しかし、そ...
続きを読む -
姿勢制御
姿勢制御の臨床を変える「進化」の視点とは?―二重伸展から足部アーチまで徹底解説

はじめに:なぜ“進化”が臨床に必要なのか 姿勢制御に進化は関係ある?現場でよく見る「立てない・座れない」の再解釈 ヒトの...
続きを読む
